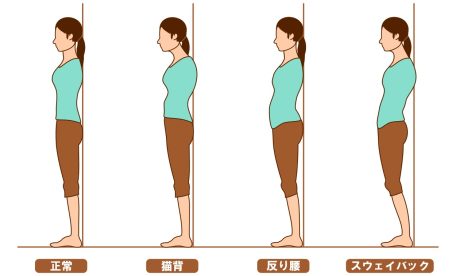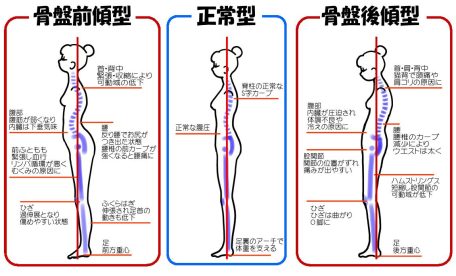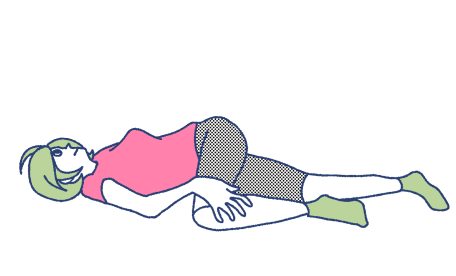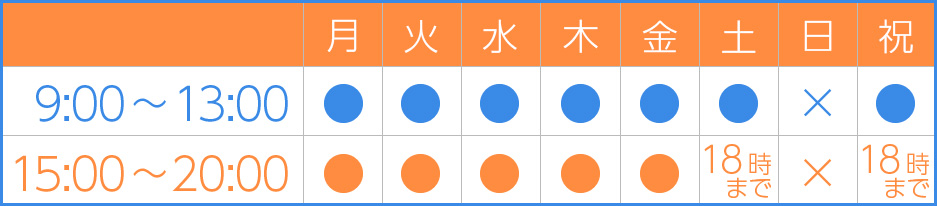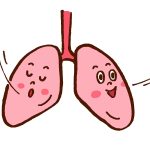人の体には中枢神経と末梢神経の2種類の神経があります。
このふたつは人の体で重要な役割を果たしているので、
神経に障害があると痛みを感じたり・感覚がおかしくなったり、体が動かなくなるなど
体にとっていろいろと不都合なことが起こります。
そこで末梢神経障害と絞扼性神経障害の違いについて解説をしていきます。
末梢性神経障害は、末梢神経系(脳および脊髄からなる中枢神経系以外の神経)に影響を及ぼす疾患の総称です。
末梢神経は、感覚、運動、自律神経機能を司る役割を持ち、体内のさまざまな部位に情報を伝達します。
この障害が起こると、しびれ、痛み、筋力低下、感覚異常などの症状が現れます。
絞扼性神経障害は、末梢神経が特定の部位で圧迫(絞扼)されることにより生じる神経障害です。
神経が骨、筋肉、腱、靭帯などの構造物によって圧迫されると、神経の機能が損なわれ、感覚異常や運動障害が起こります。
ここまでを確認すると気が付いている人もいると思いますが、意味が重なる部分があります。
末梢神経障害の枠組みの中に絞扼性神経障害があります。
末梢神経障害を細かく分けると障害の原因や範囲によって、
単一の神経(単神経障害)・複数の神経(多発神経障害)・広範な神経(多発性神経炎)になります。
絞扼性神経障害は末梢性神経障害の一種であり、局所的な神経圧迫に起因するため、
単神経障害として分類されることが多いです。
末梢性神経障害と絞扼性神経障害の違いと関連性
範囲の違い:末梢性神経障害は全身的または広範な神経障害を指し、絞扼性神経障害は特定の部位での局所的な圧迫による障害に限定される。
□原因の違い 末梢性神経障害は多様な原因(代謝性、感染性、遺伝性など)を持つが、絞扼性神経障害は主に物理的圧迫が原因。
□症状の分布 末梢性神経障害は両側性または広範な症状が多く、絞扼性神経障害は特定の神経支配領域に限定される。
□関連性 絞扼性神経障害は末梢性神経障害の一形態であり、例えば糖尿病患者では神経が圧迫に弱くなり、絞扼性神経障害を合併しやすい。