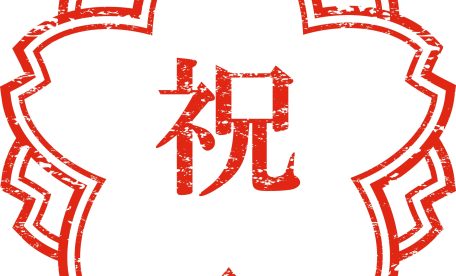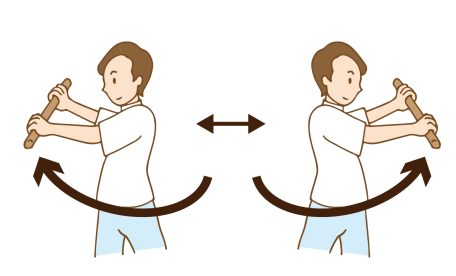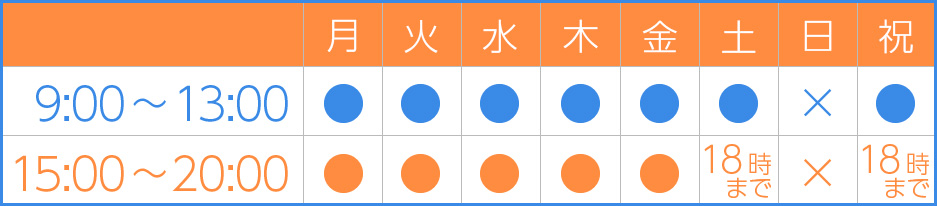秋の気持ちのいいシーズンはほぼ無く、暑いから寒いに一気に変わってきました。
気温自体が低くなったことよりも、気温差が大きいので寒さを感じます。
このような時季になる不思議な事にギックリ腰になる人が増えてくるような気がします。
理屈はいろいろと言われていることがあるので紹介をしていきます。
□気温が急に下がると、体は体温維持のために皮膚表面の血管を収縮させ(末梢血管収縮)、熱の放散を抑えます。
これにより筋肉への血流が減少し、酸素や栄養の供給が減ります。
そうすると筋肉は硬く、柔軟性を失った状態になり、ちょっとした動作(くしゃみ、重い物を持つなど)で急激に負荷がかかると損傷しやすくなります。
特に腰回りの筋肉(脊柱起立筋、腰方形筋など)は、姿勢維持に常に使われており、血流不足で硬直するとギックリ腰の引き金に。
逆に、暖かい環境から急に寒い場所へ移動すると、筋肉が「急冷」されて収縮し、微細な筋線維の損傷(微小断裂)が起こりやすくなります。
□気温低下は関節周囲の滑液(関節液)の粘度を上げるため、関節の動きがぎこちなくなります。
腰椎の椎間関節や仙腸関節は、日常動作で微妙に動いていますが、寒さで関節が「固まる」と、急な動きで関節包や靭帯が過伸張され、炎症を起こします。
これが「腰が抜けた」「ピキッと音がした」といったギックリ腰の典型的な発症パターンです。
□寒暖差が大きいと、自律神経(交感神経・副交感神経)が過剰に反応します。
寒い → 交感神経が優位 → 筋肉が緊張
暖かい → 副交感神経が優位 → 筋肉が緩む
この急激な切り替えが繰り返されると、筋肉の緊張・弛緩のリズムが乱れ、常に軽い緊張状態が続くようになります。
疲労が蓄積し、ちょっとしたきっかけで筋肉が「限界」を超える → ギックリ腰発症。
このように気温の変化が大きくなると少しは体に負担が掛かります。
その結果、体が耐えらる許容を超えてしまうとギックリ腰を発症しやすくなるので、
普段から体を動かして体が変化に対応できるようにすることが予防につながるかもしれません。