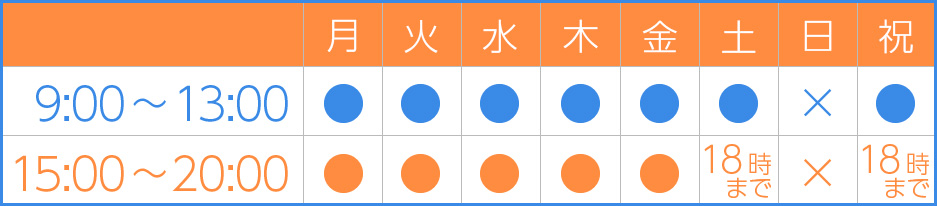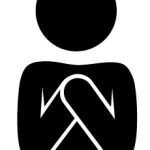いよいよ、暑かった日々も終わりつげ、涼しくなってきて熱中症という言葉も聞かなくなりました。
秋っぽさは少ない感じもありますが、日常を過ごす上では体は楽になったと言えます。
そうすると必然的に水分を摂る量が減ってきます。
そして、知らず知らずのうちに脱水症状になってしまうことも少なくありません。
特に暖房の効いた室内では、湿度が20~30%程度まで低下することがあり、肌や粘膜から水分が蒸発しやすくなります。
さらに、冬は汗をかく機会が少ないと感じ脱水に陥りやすいです。
これからの季節も水分補給はこまめに行っていかなければなりません。
そこで、冬にも起こる脱水症状について知識を深めていきましょう。
□冬の脱水症状の特徴とリスク 脱水症状の初期症状には、口の渇き・頭痛・めまい・倦怠感・尿量の減少や濃い色の尿などがあります。冬はこれらの症状を「寒さのせい」や「疲れのせい」にしがちなります。このような事も冬は血液の粘度が上がりやすく、脱水が心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めることも指摘されています。
注意すべきポイントは
□水分摂取の意識 冬は喉の渇きを感じにくいため、意識的に水分を摂ることが重要です。1日に必要な水分量は体重や活動量によりますが、成人の場合、1.5~2リットルを目安にしましょう。
□室内の湿度管理 暖房による乾燥を防ぐため、加湿器を使用したり、濡れたタオルを室内に干すなどして湿度を40~60%に保つよう心がけましょう。
□服装と発汗を考える 厚着による発汗も脱水の原因になります。暖房の効いた室内や電車内では汗をかきやすいため、脱ぎ着しやすい服装を選び、こまめに汗を拭き取る習慣をつけましょう。
□食事での水分補給 スープや味噌汁、鍋料理など温かい食事を取り入れることで、自然に水分を補給できます。
高齢者は喉の渇きを感じる感覚が鈍くなり、脱水に気づきにくい傾向があります。
また、持病(糖尿病や心臓病など)がある人は脱水が病状を悪化させるリスクが高いため、
定期的な水分摂取を家族や介護者が促すことが重要です。
子どもも体内の水分比率が低く、脱水になりやすいため、保護者が水分摂取を管理しましょう。
もちろん、誰にでも起きる可能性はあります。