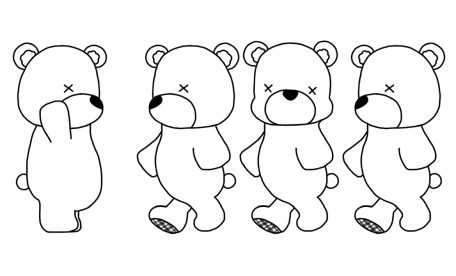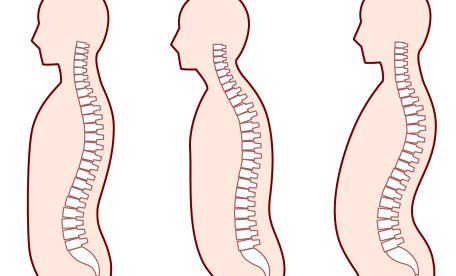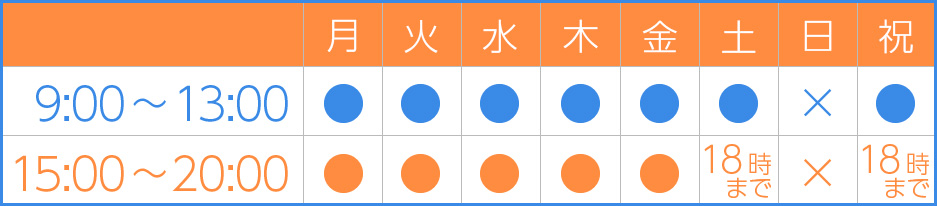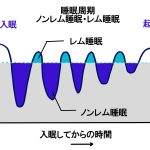前回に続いて、摂食障害の話を進めていきます。
摂食障害には、拒食症と過食症があることが分かったと思います。
これらの治療はどうするのか。
拒食症と過食症になり得る原因から紐解いていきます。
単一の原因ではなく、生物学的、心理的、社会的要因が絡み合って発症します。
□生物学的要因 遺伝的要因や脳内のセロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質の異常が関与するとされています。特に、家族に摂食障害の既往がある場合、発症リスクが高まります。
□心理的要因 完璧主義・低い自尊心・強い自己批判・ストレスへの対処困難などが関与します。トラウマや虐待の経験もリスク要因です。
□社会的要因 メディアや社会が「痩せていることが美しい」とする価値観が影響します。特に、若年層はSNSや広告の影響を受けやすく、体型へのプレッシャーを感じやすいです。
治療は、患者の症状の重症度・併存疾患(うつ病や不安障害など)・年齢や生活環境に応じて変わります。
主な要素として
□心理療法 歪んだ食行動や体型認識を修正。
□医療的介入 身体的合併症の管理。
□栄養指導 健康的な食事習慣の確立。
□社会的支援 家族やコミュニティのサポートを取り入れる。
主な治療方法
□認知行動療法(CBT) 特に過食症や過食性障害に有効。患者が自分の食行動や体型に関する歪んだ思考
(例:「太ることは失敗」)を認識し、健康的な思考や行動に置き換えることを目指します。
CBT-E(摂食障害向け認知行動療法)は、過食発作の引き金を特定し、対処法を学ぶのに効果的です。
□家族ベースの治療(FBT) 特に若年層の拒食症患者に有効。家族が治療過程に参加し、患者の食事管理や心理的サポートを担います。
親が食事のコントロールを一時的に引き受け、徐々に患者の自律性を高めます。
□対人関係療法(IPT) 対人関係の問題(例:家族や友人との葛藤)が摂食障害の引き金となる場合に有効。人間関係の改善を通じて症状を軽減します。
□精神力動的療法 無意識の感情やトラウマが摂食障害に関連する場合に用いられ、自己理解を深めることで症状を緩和します。
また、身体に深刻な影響があるので医療的管理が必要になります。
□入院治療: 重度の低体重・心血管系の問題・自殺リスクがある場合は入院が必要。入院中は栄養補給(経口または経鼻チューブ)を行い、生命を維持。段階的に体重回復を目指します。
□薬物療法 うつ病や不安障害・強迫性障害が併存する場合は選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)などの抗うつ薬が処方されることがあります。ただし、薬物単独では摂食障害の根本的治療には不十分で、心理療法と併用が推奨されます。