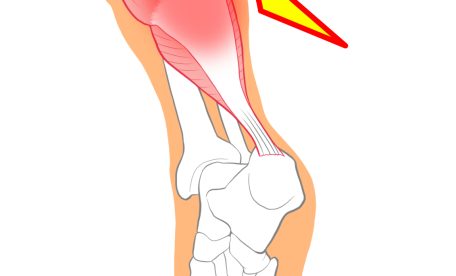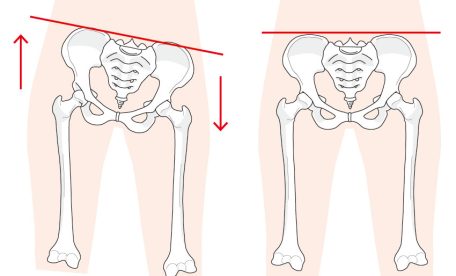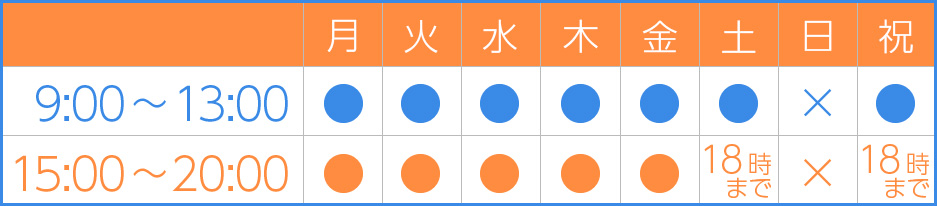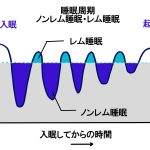日常生活を送っていく上で、食べることは生命を維持するために必要不可欠になります。
食べる行為自体は健康な状態であれば、自然と湧き上がってくる欲求があります。
しかし、体調を崩したりすると食欲が出てこないこともあります。
これは誰でも経験があると思います。
たとえば、風邪をひいて熱が高い時などがあたります。
ただ、風邪が治れば、食欲も出てくるので、一時的なものといえます。
世の中には食べること自体に問題が生じてしまうケースがあります。
それを摂食障害といいます。
聞いたことがある人もいると思いますが、イメージは食べる事ができなくて痩せきっている人ではないでしょうか。
イメージ以外のケースもあるので、少し解説をしていきます。
摂食障害の種類
拒食症(神経性食欲不振症)は、体重増加への強い恐怖から極端な食事制限を行い、低体重になる状態です。
自分の体型を歪んで認識し、痩せていても「太っている」と感じることが多いです。
主な特徴は、過度なダイエット、過剰な運動、自己誘発性嘔吐や下剤の使用などです。
過食症(神経性過食症)は、短時間に大量の食事を摂取する過食発作と、その後に嘔吐や下剤使用、過剰な運動などでカロリーを排出しようとする「排出行動」を繰り返す疾患です。
過食と排出のサイクルに強い罪悪感や自己嫌悪を伴います。
過食性障害過食性障害は、過食発作を繰り返すものの、排出行動を伴わない状態です。
感情のストレスや退屈感が引き金となり、コントロールできない食欲に駆られ、過度に食べる傾向があります。
摂食障害は身体と心の両方に深刻な影響を及ぼします。
□身体的影響
拒食症では、低体重による無月経・心拍数低下・骨密度低下・臓器不全などが生じます。
過食症では、嘔吐による歯のエナメル質の損傷・電解質異常・消化器系の障害が起こり得ます。
過食性障害では、肥満や糖尿病、高血圧などのリスクが高まります。
□心理的影響 うつ病、不安障害、強迫性障害、自己否定感、孤立感などが一般的です。
社会的な孤立や人間関係の悪化もよく見られます。
□社会的影響 学業や仕事のパフォーマンス低下、家族や友人との関係悪化などが起こり、生活全般に影響を及ぼします。