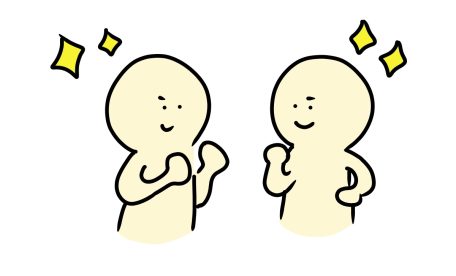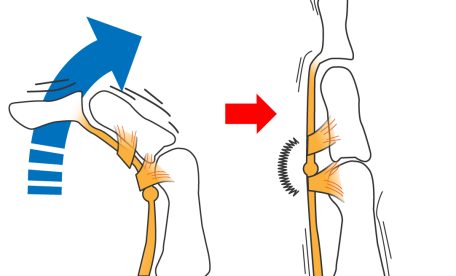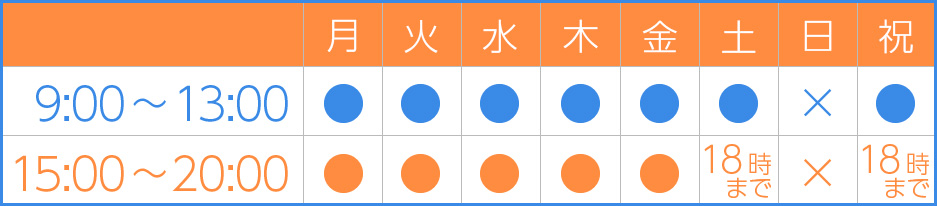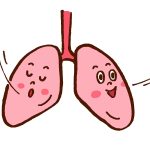今の世の中はたくさんの刺激があるので数十年前と比較してもいろいろな事に対して選択肢があります。
多様化という言葉まで出てきているので情報の量が増えていることは実感できるのではないでしょうか。
この情報の量が体の不調をきたす原因になったりもします。
これを情報疲労といって、現代のデジタル社会で急速に広がる心理的・身体的な症状を指す概念です。
目から入ってくる情報の量が多すぎるために、脳が処理しきれなくなり、疲労感や集中力の低下、意思決定の困難が生じる状態になります。
WHO(世界保健機関)も関連する「デジタル疲労」を精神的健康問題として認識しており、
2023年の調査では、世界の成人の約40%が日常的にこの症状を自覚しています(Pew Research Center)。
情報疲労の根本原因は、情報の「量」と「速度」の爆発的な増加にあります。
昔は新聞やテレビで1日数回の情報摂取で済みましたが、今はスマートフォンが常時通知を送り、
SNSのフィードが無限にスクロールされます。
例えば、1日の平均画面時間は7時間以上(Nielsen報告、2024年)で、これにより脳は1日あたり数テラバイトのデータを処理しようとします。
人間の脳は進化的に、1回の会話で数百語程度の情報を扱うよう設計されているため、このギャップが疲労を招きます。
主な症状は身体的・認知的・感情的な側面に及びます。
□目の疲れ(ドライアイや視力低下) 長時間のスクリーン凝視でまばたきが減少し、涙の蒸発が増える。
□頭痛や肩こり 姿勢の悪化と緊張から起こる。
□集中力の低下 マルチタスク(例: メールと動画の同時処理)で脳のワーキングメモリがオーバーロード。スタンフォード大学の研究(2009年)では、ヘビーユーザーはシングルタスク時の効率が40%低下すると指摘。
□記憶力の低下 情報が浅く速く流れるため、長期記憶への定着が難しくなる。「Google効果」(Sparrow et al., 2011)として知られ、必要な情報を「検索すればいい」と脳がオフライン化。
□意思決定の疲弊 選択肢の多さ(例: Netflixの数千本の動画)で脳の前頭葉が消耗する。
□イライラや不安 情報の多様性ゆえの「FOMO(Fear Of Missing Out、取り残される不安)」が常態化。SNSの比較文化が自己肯定感を低下させる。
□無力感やうつ傾向 フェイクニュースやネガティブ情報の洪水で、世界観が歪み、精神的疲弊を招く。