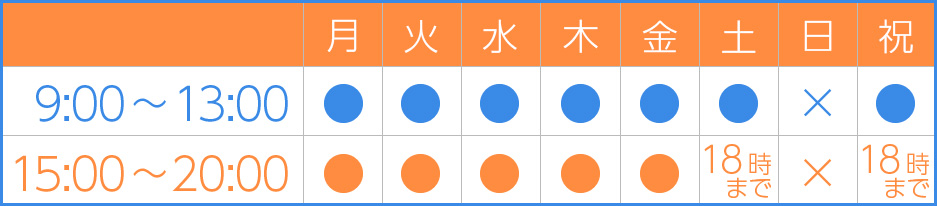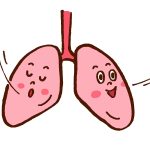医学というと病気やケガなどで悪くなった部分をよくする・回復させるといった治療をイメージする場合が多いとおもいます。
ただ、予防に主眼にを置いている予防医学というものがあります。
これは病気を未然に防ぐことを目的とした医学の一分野で、健康を維持・増進するための科学的アプローチを重視します。
病気の発症や進行を防ぐために、個人の生活習慣や社会環境を改善し、早期発見・早期介入を行うことで、医療負担の軽減や生活の質(QOL)の向上を目指します。
予防医学の目的は個人の健康寿命を延ばし、医療費の削減や社会全体の健康水準の向上を図ることになります。
特に現代社会では、生活習慣病(糖尿病、高血圧、心疾患など)や感染症・がんなどが大きな健康課題となり、
これらを予防することで個人と社会の負担を軽減するとかんがえられます。
予防医学は、介入のタイミングや目的に応じて、一次予防、二次予防、三次予防の3つに分類されます。
□一次予防 病気が発生する前に健康を維持・増進する取り組みです。
具体的には、健康教育・栄養指導・運動促進・禁煙キャンペーンなどが含まれます。
例えば、バランスの良い食事や定期的な運動は生活習慣病のリスク低減につながります。
また、職場や学校でのストレス管理プログラムも、精神的健康を保つ一次予防の一環です。
□二次予防 病気の早期発見・早期治療を目的とし、症状が現れる前または初期段階で介入します。
健康診断やがん検診(マンモグラフィー、大腸内視鏡など)が代表例です。
これにより、例えば乳がんや大腸がんを早期に発見し、治療の成功率を高めたり、進行を防いだりできます。
二次予防は、症状がない段階での積極的なスクリーニングが重要で、特に高リスク群(例:家族歴のある人、喫煙者)に対する定期検診が推奨されます。
□三次予防 すでに発症した病気の進行や再発を防ぎ、合併症を最小限に抑えることを目指します。
リハビリテーション、薬物療法、患者教育などがこれに該当します。
例えば、心筋梗塞後の患者に対する運動療法や食事管理は、再発防止やQOL向上に役立ちます。また、糖尿病患者の血糖コントロール指導も三次予防の一例です。
気になる人は専門家に相談しましょう。