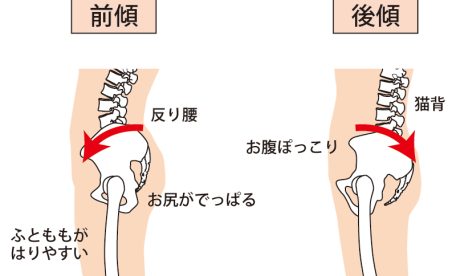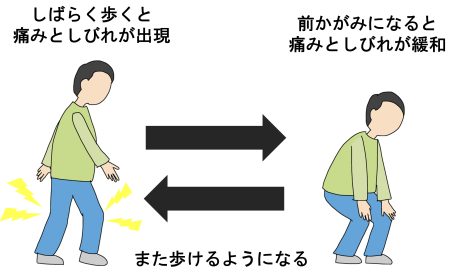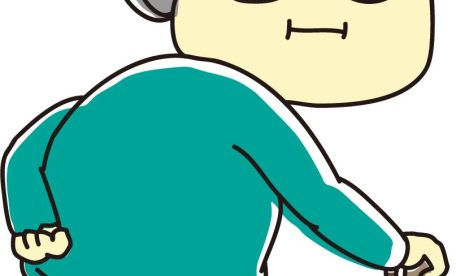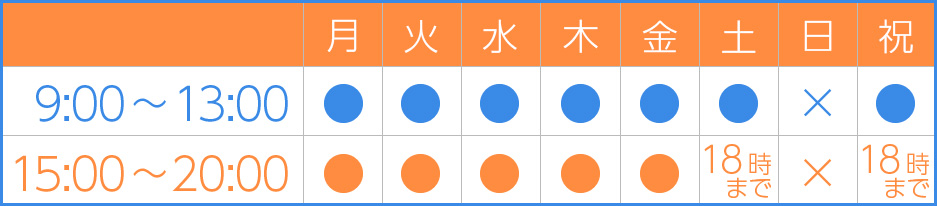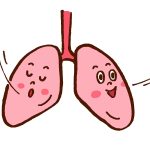前回、野球肘について話をすすめましたが、治療やリハビリについては触れていないので、
どのような経過を辿って復帰していくのかを紹介していきます。
肘の状態によって、保存療法と手術療法に分かれます。
いろいろと調べていくと
□保存療法:約70~90%(特に成長期の選手や軽~中程度の症例で主流)
□手術療法:約10~30%(重症例やプロ選手で増加)
このように手術になることは稀になります。
保存的治療のリハビリテーション保存的治療は、軽度~中等度の野球肘(例:内側上顆炎や軽度の靭帯損傷、離断性骨軟骨炎の初期)に対して適用されます。
リハビリは段階的に進行して、通常3~6か月程度かかります。
具体例
□フェーズ1 急性期(痛みと炎症の管理・0~4週間)
目的 炎症と痛みを抑え、肘の安静を保つ。
投球の完全休止。肘へのストレスを避けるため、投球やスイングを禁止。軽いキャッチボールも控える。
アイシングを1日2~3回、15~20分間、肘にアイスパックを当てる(直接肌に当てないよう注意)。
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を医師の指導のもとで使用する場合ある。
肘を安定させるサポーターやブレースを装着し、負担を軽減する。
軽い運動で、痛みのない範囲で肘の屈伸や前腕の回内・回外をゆっくり行う(例:1日10回、3セット)。
注意点 成長期の選手では、骨端線の損傷を防ぐため、無理な動きを避ける。
□フェーズ2 回復期(筋力・柔軟性の回復・4~8週間)
目的 肘の可動域を正常化し、周辺筋の強化を始める。
方法 ストレッチング: 前腕(屈筋・伸筋)・肩・胸部の筋肉を対象に、痛みのない範囲で柔軟性向上を目指す(例:リストストレッチ、肩の外旋ストレッチ)。
等尺性運動 肘を動かさずに筋力を維持する運動(例:前腕を固定し、軽く握力をかける、10秒×10回)。
体幹・下半身強化 プランクやスクワットで体全体の安定性を高め、肘への負担を軽減する。
低負荷の有酸素運動 ランニングやサイクリングで全身の血流を促進し、回復を助ける。
注意点 痛みが再発したら即座に運動を中止する。
□フェーズ3 機能回復期(投球復帰準備、8~12週間)
目的 投球動作に必要な筋力と動きを回復。
方法 動的筋力トレーニング: 軽いダンベル(1~2kg)やセラバンドを使った前腕・肩の強化(例:リストカール、肩の外旋運動)。
投球メカニクス修正 コーチや理学療法士と連携し、肘に負担の少ないフォームを練習。ビデオ解析を活用する場合もある。
段階的投球プログラム(ITP: Interval Throwing Program)軽いキャッチボールから開始(例:10mで10投、痛みがなければ距離や回数を徐々に増やす)。
注意点 投球再開は医師や理学療法士などの許可が必要。急な負荷増加は再発リスクを高める。
□フェーズ4:復帰期(12週間以降)
目的 競技復帰と再発防止。
ピッチングを徐々に再開(例:30~50%の力で20球から開始)。投球数は週ごとに5~10%増加させる。
全身コンディショニング: 肩・背中・下半身の筋力維持と柔軟性向上を継続。
定期評価で投球後の痛みや可動域をチェックし、必要ならフォームを再調整を行う。
復帰目安:の痛みなく通常の投球(70~100球)が可能になるまで3~6か月。
これが保存療法による復帰の目安になる。