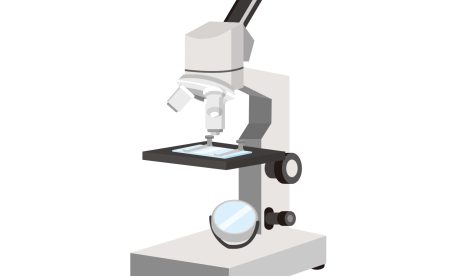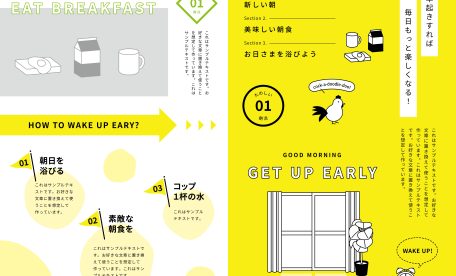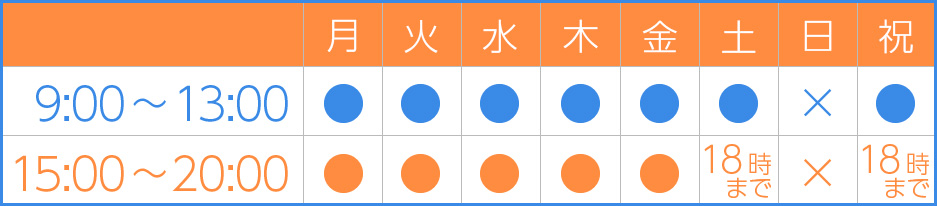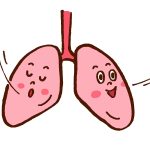汗をかくって意識をして行うことではなく、無意識に行うことができる体に備わった機能のひとつになります。
暑いと汗をかいて体内から水分が失われるイメージが強いと思いますが、水分は常に体から減っています。
このことを不感蒸泄といいます。
体内から必要以上に水分を失ってしまうと脱水症状になってしまいます。
体にとって水分は大切なものになるので、脱水症状についての知識を整理します。
脱水症状とは、体内の水分と電解質(ナトリウム、カリウムなど)が不足し、正常な生理機能が維持できなくなる状態を指します。
脱水状態は体内からどの程度、水分を失うのか。
□軽度(体重の1〜3%の水分喪失)
口の渇き、喉の渇き
尿量の減少、尿の色が濃くなる
軽い疲労感や頭痛
□中度(体重の4〜6%の水分喪失)
強い喉の渇き、口や皮膚の乾燥
めまい、立ちくらみ
心拍数の増加、血圧低下
集中力の低下、イライラ
□重度(体重の7%以上の水分喪失):意識障害、錯乱
極端な疲労感、筋肉のけいれん
ショック状態(急速な心拍数低下、血圧低下)
臓器不全や昏睡のリスク
この数値を参考にすると例えば体重50㎏の人だと1%水分を失うと500ml(だいたいペットボトル1本分)で
脱水状態になります。
この数値は不感蒸泄でも水分喪失量は1日あたり約500〜1000mLあると言われているので
汗を少しでもかいているとすぐ脱水状態になってしまうことは理解できると思います。
脱水症状は体に異変を感じていなくても起きることなのです。
だから、「のどに渇きを感じる前に水分を摂りましょう。」と言われるのは
このような理論を基に言われています。
脱水症状を防ぐには、
□適切な水分補給 気温が高い日や運動時には、こまめに水や電解質を含む飲料を摂取する。1日あたり1.5〜2Lの水分を目安にする(活動量や環境で変化)。
□環境管理: 高温多湿な場所では休息をこまめに取り、風通しの良い場所で過ごす。エアコンや扇風機を活用する。
□食事 果物や野菜など水分を多く含む食品を取り入れる。塩分も適度に摂取し、電解質バランスを保つ。
□リスクの高い人のケア 高齢者や子どもは自ら水分不足に気づきにくいため、周囲が積極的に水分摂取を促す。
脱水症状は意識ひとつで防ぐことができるので実践しましょう。