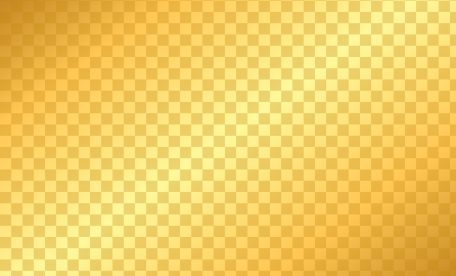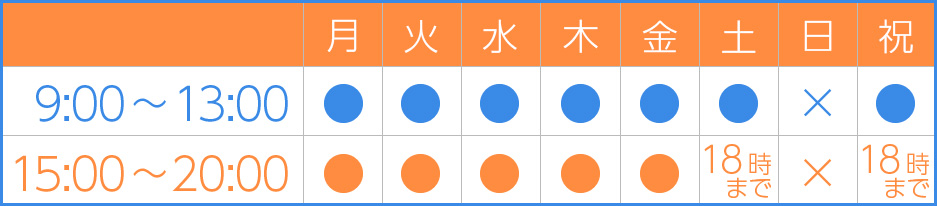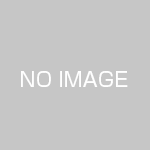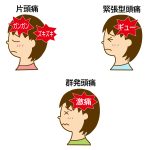前回は紫外線から皮膚を守るために対策をしましょうという内容でした。
今回は紫外線と皮膚の関係について解説をしていきます。
昭和の頃は日に焼けることが医学的にビタミンDを生成するので、くる病の予防になることが分かっていたので、
ビタミンDの重要性が強調され、日光浴が推奨され、学校や地域で「日光浴」が健康法として取り入れられ、
屋外活動が奨励されました。
しかし、平成から令和にかけて、日焼けに対する認識は劇的に変化し、「体に悪い」と言われるようになりました。
これは医学が進歩したことによって新たな真実が明らかになってきたからです。
1980年代以降、紫外線が皮膚がんのリスクを高めることが、世界的な研究で明らかになりました。
オーストラリアなど紫外線が強い地域での皮膚がん増加が注目され、WHOや各国保健機関が紫外線対策を提唱するようになりました。
紫外線はDNAを損傷し、細胞のがん化を誘発するだけでなく、免疫系にも影響を与えることが判明しました。
これが一般にも知られるようになりました。
オゾン層は地球を有害な紫外線から守る役割を果たします。
1980~1990年代、オゾン層の破壊が国際的な問題となり、紫外線量の増加が懸念されました。
日本でも、紫外線量の増加が健康リスクとして報道され、日焼け止めやUVカット製品の需要が急増しています。
このような事から予防医学の考え方が浸透し、紫外線対策が健康管理の一部となりました。
厚生労働省や日本皮膚科学会は、帽子やサングラス、日焼け止めの使用を推奨しています。
学校教育でも、熱中症予防と並んで紫外線対策が指導されるようになりました。
2020年代には、気候変動による夏の暑さや紫外線量の増加がさらに注目され、屋外活動時の保護が常識化しています。
日焼けに対する認識の変化は、「健康の象徴」から「健康リスク」になっています。
しかし、紫外線対策をしながら適度な日光を取り入れことを忘れないようにしましょう。