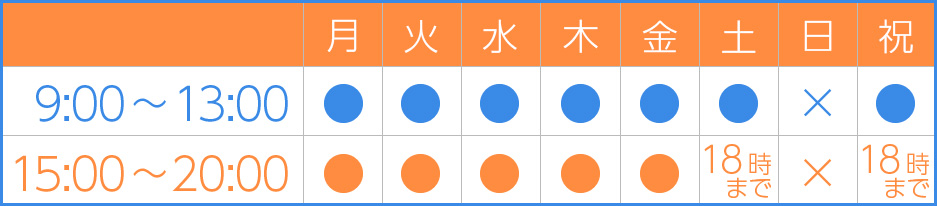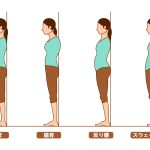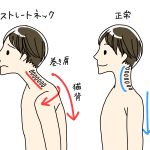前回は認知行動療法がどういったものなのかを紹介しました。
認知行動療法は慢性痛の改善にも活用されているのでこちらの話を進めていきます。
慢性痛は器質的に異常がみられないもしくは器質的損傷以上の痛みを感じることが3ヵ月以上続く痛みを指します。
特に慢性痛は身体的な要因だけでなく、心理的・社会的要因も関与するため、CBTはその心理的側面に焦点を当てて効果を発揮します。
慢性痛は、腰痛、線維筋痛症、関節炎、頭痛、神経障害性疼痛など、さまざまな疾患に関連しています。
これらの痛みは、単に身体的な問題だけでなく、ストレス、不安、うつ、睡眠障害、活動制限といった心理的・行動的要因によって悪化することがあります。
慢性痛を抱える人は、「痛み=危険」「動くと悪化する」といった非適応的な思考(認知の歪み)を持つことがあります。
そこで、痛みの認知の修正をすることになります。
例えば「痛みは必ずしも悪化を意味しない」「適度な運動は回復を助ける」といった現実的な視点に変えることで、痛みに対する過剰な恐怖や回避行動を減らします。
痛みのために活動を避ける(回避行動)ことは、筋力低下や気分低下を招き、痛みをさらに悪化させる悪循環を引き起こします。
CBTでは、段階的な活動計画(例:軽いストレッチや散歩)を立て、活動量を増やすことでこの悪循環を断ち切ります。
痛みが起きた際の対処法(例:気をそらす、ポジティブな自己対話)を学び、痛みに振り回されない生活習慣を構築します。
これにより、痛みが生活全体を支配する感覚が軽減されます。
そして、多くの研究が、慢性痛に対するCBTの有効性を支持しています。
CBTの効果
□痛みの強度の軽減 CBTは痛みそのものを完全に取り除くわけではありませんが、痛みの知覚や耐性を改善します。
□生活の質の向上 痛みによる活動制限が減り、仕事や趣味、社会活動への参加が増えたりする。
□心理的症状の改善 うつや不安の症状が軽減し、睡眠の質も向上する傾向があります。
□自己効力感の向上 CBTを通じて、患者は「自分で痛みを管理できる」という自信(自己効力感)を得られ、依存的な行動が減少します。
慢性痛の治療目的は痛みの除去ではなく、QOLの向上が最大の目的になります。
ただ、QOLの向上が痛みの除去につなぐることも少なくありません。