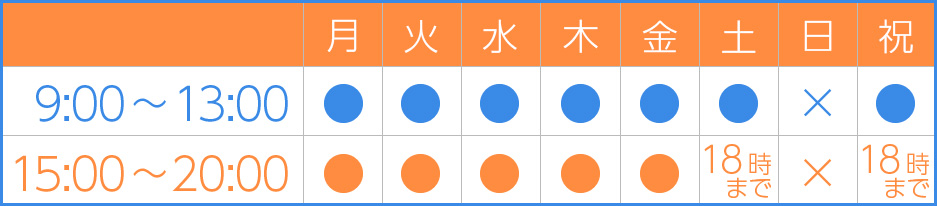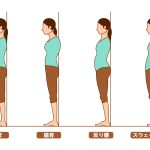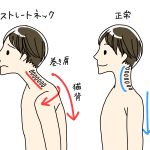身体の調子が悪いというとさまざまな見方ができますが、そのひとつに周りから見た目で判断できるのかがあります。
たとえば、ケガをして包帯など使用している・動きが緩慢で辛そうにしていれば、調子が悪いのだろうと想像できると思います。
しかし、心理的にダメージを受けてたり・免疫やホルモン系など体の内部で起きている調子の悪さは見た目で判断出来ることは少ないです。
見た目で分からないもので、問題になりがちな事に「優先席を若い人が座っている」があります。
このよう場合も見た目で判断できない調子の悪さをもっているかもしれません。
今回は見た目で判断できない調子の悪さで心理面が大きく関わっている時に使われる認知行動療法について紹介をしていきます。
認知行動療法はCognitive Behavioral TherapyともいいCBTと略されます。
CBTの基本原理は、「思考が感情や行動に影響を与える」という考え方です。
人は状況を直接的に感じるのではなく、その状況に対する自分の解釈や思考を通じて感情や行動を形成します。
例えば、失敗した際に「自分は無能だ」と考える人は落ち込みや無気力に陥りやすいですが、
「失敗は学びの機会だ」と捉えれば前向きな行動を取りやすくなります。
CBTでは、このような「非適応的な思考(認知の歪み)」を特定し、より現実的で建設的な思考に変えることで、感情や行動を改善します。
CBTの主な技法
□認知再構成法 自動的に浮かぶ否定的な思考を特定し、その妥当性を検討した上で、よりバランスの取れた思考に置き換える技法です。
□行動活性化 うつ病などで活動量が低下している場合、行動を少しずつ増やすことを目指します。
□曝露療法 不安障害や恐怖症に対して有効で、恐れている対象や状況に段階的に向き合う技法です。
□問題解決技法 ストレスや問題に対処するための構造化されたアプローチです。問題を明確に定義し、解決策をブレインストーミングし、最適なものを選んで実行します。
□マインドフルネスやリラクゼーション ストレスや不安を軽減するため、呼吸法や瞑想、筋弛緩法などを取り入れることがあります。
精神科や心療内科で提供されることが多いです。