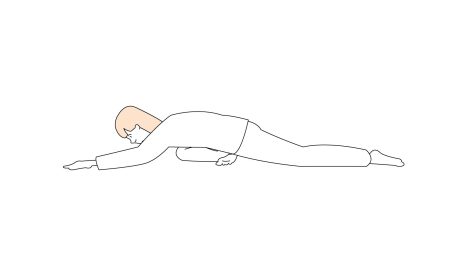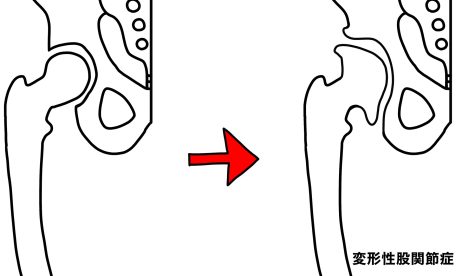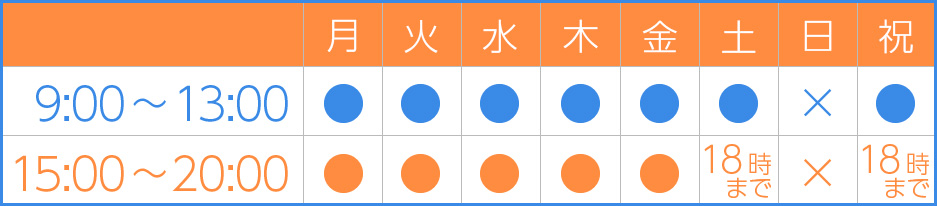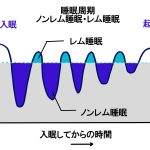病気になった時、薬を服用して体の回復を図ることも少なくありません。
この時は、痛み止め・抗生物質など原因に合せて、薬が選択されます。
たくさんの種類があるくするですが、風邪を治す薬はないと聞いたことがあると思います。
風邪はおもにウィルスが原因になります。
この他に体の具合を悪くするものに細菌があります。
ウィルスと細菌の違いについて、整理をしていきます。
細菌は単細胞の生物で、細胞壁、細胞膜、細胞質、DNAなどの基本的な細胞構造を持ち、自己増殖が可能です。
細菌の大きさは一般的に0.5~5マイクロメートル程度で、光学顕微鏡で観察できます。
一方、ウィルスは生物と非生物の中間的な存在で、細胞構造を持たず、自己増殖能力もありません。
ウィルスは遺伝子(DNAまたはRNA)とそれを包むタンパク質の殻(カプシド)で構成され、
一部のウィルスはさらに脂質膜(エンベロープ)を持つこともあります。
大きさは20~400ナノメートル程度で、細菌の10分の1から100分の1程度と非常に小さく、電子顕微鏡でしか観察できません。
菌による感染症は、細菌そのものが増殖し、毒素を産生したり、組織を直接傷つけたりすることで発症します。
代表的な疾患には、肺炎(肺炎球菌)、結核、食中毒(サルモネラ菌や黄色ブドウ球菌)などがあります。
症状は発熱、炎症、膿の形成などが一般的です。
ウィルスによる感染症は、宿主細胞の破壊や免疫反応の過剰な活性化によって引き起こされます。
風邪、インフルエンザ、肝炎、エイズ、新型コロナウィルス感染症などが例です。
ウィルス感染では、発熱、倦怠感、筋肉痛、咳などの全身症状が目立つことが多いです。
感染症の治療には、抗生物質(ペニシリンやエリスロマイシンなど)が一般的に用いられます。
抗生物質は細菌の細胞壁合成やタンパク質合成を阻害し、細菌を殺すか増殖を抑えます。
ただし、耐性菌の増加が問題となっており、適切な使用が求められます。
ウィルス感染症の治療には、抗ウィルス薬(例:インフルエンザに対するタミフル、HIVに対する抗レトロウィルス薬)を使用する場合がありますが、種類は限られています。
多くのウィルス感染症では、ワクチンによる予防や、免疫系が自然にウィルスを排除するのを待つ対症療法が中心です。