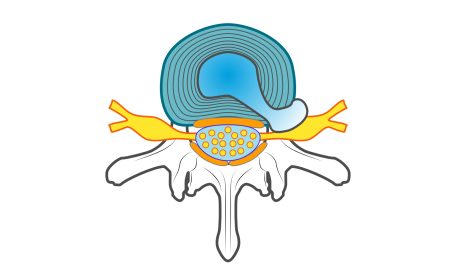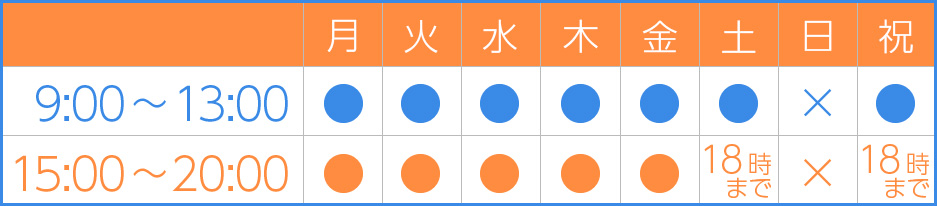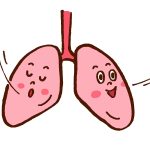前回は脱水症状について話をしました。
のどに渇きを感じたら軽度の脱水状態になので、日常のどのタイミングでも脱水状態になることがわかります。
身体から水分が減らなければ脱水状態にはならないのですが、そのような事はありません。
身体から水分が減ったとしても大切な役割をしていることのひとつに「汗をかく」ということがあります。
一見、非効率にも感じかねない身体の機能ですが、どのような意味があるのか。
主に体温調節に関連していて、人間を含む多くの恒温動物が環境の高温に対処するための生理的な適応になります。
人間の体は、約36.5〜37.5℃の範囲で最適に機能するように設計されています。
この体温が維持されないと、酵素の働きや代謝プロセスが乱れ、最悪の場合、臓器不全や死に至る可能性があります。
気温が高い環境では、外部からの熱や運動による体内での熱産生により体温が上昇しやすくなります。
このとき、汗をかくことで体温を下げる仕組みが働きます。
汗は主に水分と少量の塩分や電解質から成り、皮膚表面で蒸発する際に熱を奪います。
この現象は「蒸発冷却」と呼ばれ、物理的に体表面の熱エネルギーを空気中に放散します。
たとえば、1gの汗が蒸発する際に約540カロリーの熱を奪うため、大量の汗をかくことで効率的に体温を下げることができます。
体温調節以外にもいくつかの副次的な効果があります。
たとえば、汗は皮膚表面の細菌や汚れを洗い流し、皮膚を清潔に保つ役割も果たします。
また、発汗により体内の一部の老廃物が排出されることもあります。
このように「汗をかく」ことは生命を維持するために大切な機能だとわかると思います。
しかし、「汗をかく」とは体内の水分を失っていくことでもあるので、
水分を補給して、バランスを取らなければなりません。
注意点としては、高温多湿な環境では汗が蒸発しにくく、効果が低下することがあり、
この場合、熱が体内にこもり、熱中症のリスクが高まります。
また、過度な発汗は脱水症状を引き起こす可能性も出てきます。