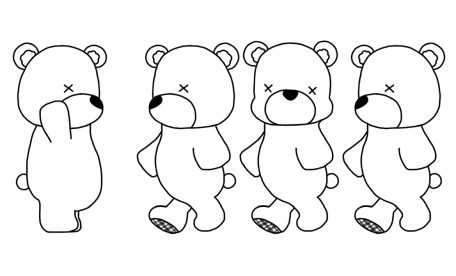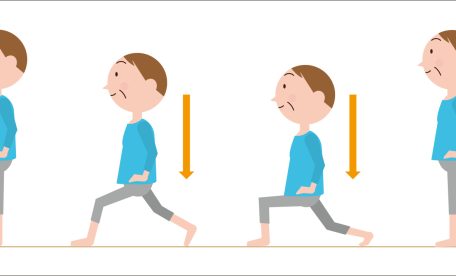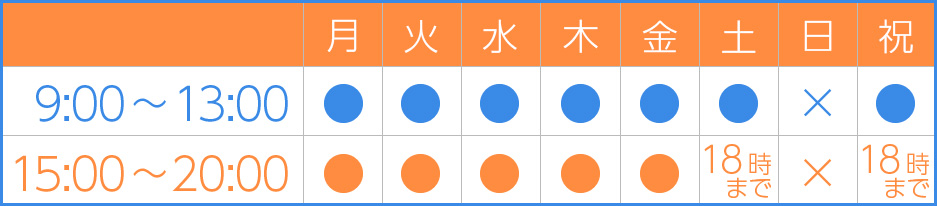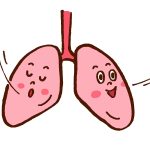睡眠が大切なことは周知の事実だと思います。
寝不足で調子がよくないことは誰でも経験しているはずです。
睡眠時間の確保や睡眠の質をよくすることは大切だと言われます。
しかし、働いていると必ずいいタイミングで就寝できるとは限りません。
そこで、比較的、睡眠障害になりやすい職業を紹介します。
□医療従事者(医師、看護師など) 夜勤や長時間勤務が頻繁で、睡眠リズムが乱れやすい。また、命に関わる責任感からストレスも高い。
□シフト制の労働者(工場勤務、コンビニ店員など) 昼夜逆転のシフトや不規則なスケジュールにより、体内時計が調整しづらい。
□トラック運転手やタクシー運転手 長時間運転や夜間勤務が多く、十分な休息が取れない場合がある。
□ITエンジニア・プログラマー 納期前後の長時間労働やデスクワークによる運動不足、ブルーライト曝露が睡眠の質を下げる可能性がある。
□警察官・消防士 緊急対応が必要なため、呼び出しや夜勤が多く、睡眠が中断されやすい。
□パイロット・客室乗務員 時差を伴う長距離移動で体内時計が乱れ、いわゆる「時差ボケ」が慢性化することがある。
特徴として、時間で業務を区切ることが難しい職業になります。
体のリズムだけで、睡眠障害になるわけでありません。
主な原因は
身体的要因
□病気や疾患 睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、慢性疼痛(腰痛や関節痛など)、喘息、胃食道逆流症(GERD)などが睡眠を妨げる。
□ホルモンの変化 更年期によるホルモン変動や甲状腺機能異常が睡眠リズムに影響を与える。
薬や物質: カフェイン、ニコチン、アルコールの過剰摂取や、特定の薬(抗うつ薬、ステロイドなど)の副作用。
心理的要因
□ストレスや不安 仕事や人間関係のプレッシャー、心配事が頭から離れず入眠困難や中途覚醒を引き起こす。
□精神疾患 うつ病、不安障害、双極性障害、PTSDなどは睡眠障害と密接に関連している。
□過労 精神的な疲弊が蓄積すると、リラックスできず睡眠の質が低下する。
環境的要因
□生活習慣の乱れ 不規則な就寝・起床時間、夜遅くまでのスマホやPC使用(ブルーライト曝露)が体内時計を乱す。
□騒音や光 近隣の騒音、明るすぎる寝室環境が睡眠を妨げる。
□時差やシフト勤務 体内時計が適応しきれず、概日リズム睡眠障害を引き起こす。
□加齢 年齢を重ねると睡眠の構造が変化し、深い睡眠(ノンレム睡眠)が減少し、夜中に目覚めやすくなる。
その他の要因
□遺伝的要因 不眠症やナルコレプシーなど、一部は遺伝的な素因が関与する可能性がある。
□過食・運動不足 夜遅くの食事や運動不足が消化不良や身体の緊張を引き起こし、睡眠に悪影響を及ぼす。
自分で対応できること・できないことがあるので、長い期間、睡眠でなやんでいるならば専門家に相談してみましょう。